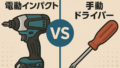気象病とは?その症状と背景
「雨が降る前に頭が痛くなる」「台風が近づくとめまいがする」…こんな経験はありませんか?それはもしかすると「気象病」かもしれません。気象病(きしょうびょう)とは、天候や気圧、湿度などの変化によって体調が崩れる現象を指す俗称で、医学的には「気象関連疾患」とも呼ばれます。
代表的な症状には以下のようなものがあります。
- 頭痛・偏頭痛
- 関節痛や古傷の痛み
- 耳鳴り・めまい
- 不眠やだるさ
- 自律神経の乱れによる体調不良
特に女性や高齢者に多く見られ、日常生活に支障をきたすケースも少なくありません。
医学的に見た気象病のメカニズム
気象病の大きな要因のひとつとされているのが「気圧の変化」です。人間の体には外部の気圧に適応するための仕組みが備わっていますが、気圧が急激に下がったり上がったりすると、内耳(ないじ)という平衡感覚を司る器官が過敏に反応し、自律神経に影響を及ぼすことがあります。
とくに気圧が下がると「交感神経」が優位になり、血管が収縮。これが頭痛や関節痛の原因になるとされています。また、自律神経のバランスが乱れることで、めまいや不眠といった不調が起こるのです。
民間説・東洋医学で語られる「気象と体」の関係
気象病は西洋医学だけでなく、東洋医学や民間療法の中でも古くから注目されてきたテーマです。
気・血・水のバランスが崩れる?
東洋医学では、体の健康は「気(エネルギー)」「血(けつ)」「水(すい)」のバランスで成り立っていると考えられています。気圧や湿度の変化によってこのバランスが崩れると、「水滞(すいたい)」や「気虚(ききょ)」といった状態になり、むくみやだるさ、痛みが生じるとされます。
天気痛は「古傷が泣く」とも言われる
また、民間説では「古傷が泣く」との表現もあります。戦国武将が雨の前に傷が痛むと言った記録もあり、気象と体の関係は長い間人々に知られてきました。現代の研究でも、過去に外傷を負った部分の神経が気圧変化に敏感になりやすいことが確認されています。
気象病に悩まないための対策法
完全に防ぐことは難しい気象病ですが、日常生活の中で取り入れられる対策もあります。
1. 気圧の変化を事前に把握する
近年では「頭痛ーる」などの気象予報アプリを使って、低気圧の接近を事前に察知できるようになっています。これにより、早めの対策(睡眠の確保・薬の準備など)が可能になります。
2. 自律神経を整える習慣をつける
- 朝日を浴びる
- 毎日同じ時間に起きて寝る
- 入浴でリラックス
- 軽い運動やストレッチ
これらの習慣は、自律神経の安定化に効果的で、気象病に強い体作りにつながります。
3. 耳を温めて内耳ケア
気圧変化に敏感な内耳をケアする方法として、耳のマッサージや温めが推奨されています。耳の周囲の血流を良くすることで、内耳の過剰な反応をやわらげる効果が期待できます。
まとめ|気象病は「気のせい」ではない
「気象病」は医学的にも研究が進んでおり、決して「気のせい」ではありません。天候による体調の変化を知ることで、正しく対処することができます。天気の変わり目に不調を感じる方は、ぜひ自分の体と天候の関係に注目してみてください。自律神経を整える生活習慣や、耳まわりのケア、アプリの活用など、できることから始めてみましょう。