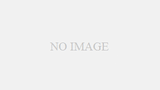身請けされた花魁「瀬川」の行く末と遊郭の現実
江戸時代の遊郭・吉原において、ひときわ美貌と芸事で名を馳せた花魁・瀬川(演:小芝風花)。彼女は江戸町一丁目にある大見世・松葉屋の五代目という名花であったが、盲目の大富豪であり権力者でもあった鳥山検校(演:市原隼人)によって、現代の価値で約1億4000万円相当の1400両という法外な金額で身請けされる。この出来事は、NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の第10話(3月9日放送)にて描かれている。
瀬川が吉原を出て鳥山検校の元に移ったことで、彼女の人生は大きく転機を迎えることになる。第11話(3月16日放送)では、「瀬以」という新しい名で登場し、すでに「人妻」となっている様子が描かれる。そんな中、蔦屋重三郎(演:横浜流星)は吉原の催し「俄」に浄瑠璃の太夫・富本午之助(演:寛一郎)を招くため、大文字屋(演:伊藤淳史)と共に鳥山検校の屋敷を訪ねる。
そこで久々に瀬川と再会する蔦重。ふたりのあいだには親密なやりとりが交わされるが、それを耳にした検校は明らかに不機嫌になり、強い嫉妬心を露わにする。蔦重からの協力依頼にも冷ややかな態度を取り、午之助を評価することも拒む様子を見せる。だが後に実際に浄瑠璃を聴いた検校は、その才能を認め、「豊前太夫」の襲名を許可。瀬川に対しては「お前の願いはすべて叶える」と不穏な響きをもった言葉を口にし、今後の展開に暗雲が立ちこめることを示唆する。
身請けは「救い」なのか、それとも新たな枷か?
吉原の遊女の多くは、幼い頃に親の借金の肩代わりとして妓楼に売られていた。数年にわたり厳しい年季奉公を強いられ、休日は年にわずか2日。過酷な環境の中で、性病や過労による健康被害が多発し、若くして命を落とすことも珍しくなかった。
そんな生活から抜け出す唯一の道が「身請け」であった。裕福な客が金銭を支払い、遊女の身柄を引き取ることで、遊郭からの解放が叶うのだ。しかしそれは、必ずしも幸せを約束するものではなかった。
瀬川の場合、安永4年(1775)に身請けされたものの、そのわずか3年後には鳥山検校が幕府の政策を悪用した高利貸しの罪により、すべての特権と財産を剥奪され、江戸から追放されてしまう。この一件によって瀬川の生活も一変し、むしろ自由を得たはずの身請けが、新たな苦しみの始まりとなった。
華やかな芸事の裏にある「家庭力の欠如」
花魁として一流の遊女たちは、舞、三味線、和歌など多岐にわたる芸を学んでいた。とくに上級遊女ほど、教養と気品を備えていたため、一部では身請け後に商家の正妻となる例も見られた。
しかし、家事に関してはほとんど経験がなく、使用人のいない家庭では正妻としての役割を果たすのが難しいという現実もあった。また、出自や過去を理由に、姑や親戚からの冷たい扱いに耐えきれず、家を出るケースも少なくなかった。
ヨーロッパの旅行者の記録では、日本の遊女は年季明けにごく普通に結婚していたと記されており、それは驚くべきことだったという。しかしながら、現実には正妻ではなく「妾」や「囲い者」として扱われる例が多く、真に平穏な家庭生活を手に入れるのは難しかった。
恋がもたらす破局——遊女を巡る凄惨な事件
身請けを巡っては、数々の悲劇も生まれた。たとえば天明5年(1785)、大菱屋の遊女・綾絹は富裕な商人に身請けされる予定だったが、彼女に入れ込んでいた旗本・藤枝教行が彼女を連れ去る。逃亡が発覚し、追手が迫る中で、藤枝は綾絹を刺殺し、自らも命を絶った。彼女はまだ19歳であった。
また、仙台藩主・伊達綱宗が太夫・高尾を身請けしたものの、彼女に拒絶されたことに逆上し、船上で殺害したという伝説も存在する。真偽は定かでないが、遊女がいかに命の危険と隣り合わせだったかを物語っている。
身請けの果てに待つ短い安らぎ
ドラマにも登場する大田南畝(演:桐谷健太)は、身分も顧みず、下級遊女・三保崎を身請けした。だがその7年後、彼女は30歳前後で病死。遊郭での日々が身体に与えた影響は大きく、性病にかかっていた遊女が多かったことも、短命の一因とされる。
稀有な幸福:瀬川のその後
瀬川については、鳥山検校の没落後に再婚し、2人の子どもを授かったという説がある。実現が困難とされる“母となる遊女”を成し遂げた稀有な例であり、もし事実であれば、彼女は比較的恵まれた人生を歩んだといえるだろう。
また、山東京伝(演:古川雄大)のモデルとなった人物も、年季明けの元遊女・菊園と結ばれた後、彼女の死後には玉の井という若い遊女を後妻に迎え、彼女とは円満な家庭生活を築いたと伝えられている。
吉原という特殊な世界の中で、身請けとは「救い」と「呪い」の両面をもつ制度であった。そこから脱する者が新たな幸福を手にできるかどうかは、運命と相手次第だったのである。
PRESIDENT Onlineより