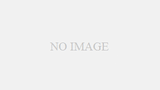NHKの朝の連続テレビ小説『あんぱん』は現在、第2週「フシアワセさん今日は」が放送されており、多くの視聴者が登場人物たちの複雑な心の動きに注目している。主人公の少女・のぶ(演:永瀬ゆずな)を中心に、朝田家の家族たちは、父・結太郎(演:加瀬亮)の死という大きな出来事を受け入れながら、それぞれの心の整理を試みている。特に印象的なのは、母の帰りを心待ちにする少年・柳井嵩(演:木村優来)が、シーソーで遊びたいとせがむ弟・千尋(演:平山正剛)に思わず厳しく接してしまうシーンだ。そこには、父・清(演:二宮和也)とのかけがえのない思い出と、それを共有できない弟に対する戸惑いや寂しさが色濃く映し出されている。
今回は、『あんぱん』の物語の背景にある実話を元に、原作者であるやなせたかし氏と、その実弟・千尋さんとの間にあった幼少期の記憶をたどっていく。
■引き裂かれた幼い兄弟、記憶のかけらをつなぐ物語
やなせたかし氏(本名:柳瀬嵩)の両親、清氏と登喜子さんは、1918年(大正7年)に結婚した。二人はともに高知県の出身で、清氏は由緒ある旧家の出身、登喜子さんは地元でも名家の娘として知られていた。当時としては珍しく、登喜子さんは再婚で、清氏はその二番目の夫となった。
1919年(大正8年)には長男の嵩さんが、そして1921年(大正10年)には次男の千尋さんが誕生し、家族4人は東京で穏やかな日々を送っていた。しかしその平穏は長く続かず、1923年(大正12年)、清氏が新聞社の特派員として中国・上海に赴任することが決まる。清氏は後に、福建省の厦門(アモイ)へと転勤となり、その間、登喜子さんは幼い二人の息子たちを連れて高知県の実家へと戻ることになる。
自然豊かな故郷の村で、嵩さんと千尋さんは野山を駆け回りながら、のびのびとした幼少期を過ごしたという。土の匂いや川の冷たさ、草の感触など、五感に刻まれる日々が兄弟を強く結びつけていた。
だが翌1924年(大正13年)、悲劇が一家を襲う。清氏が赴任先の厦門で病に倒れ、命を落としたのだ。この出来事は、幼かった嵩さん(当時5歳)と千尋さん(3歳)にとって、何が起こったのかすぐには理解できるものではなかった。ただ、梅の木の下で一緒に遊んでいた記憶、母が激しく泣き崩れる姿、そして晴れ渡る空のもと、田んぼ道を通って父の墓へと歩いた日のことが、断片的ながら心に残っていたとやなせ氏は後に語っている。
清氏の死後、兄弟の運命は大きく分かれる。清氏の兄である寛氏夫妻は、以前から子どもがなく、いずれ千尋さんを養子として迎える予定だった。その話は清氏が存命中から進められており、彼の死をきっかけに現実のものとなる。寛氏は高知で医師として開業しており、経済的にも安定していたことから、千尋さんはその家で大切に育てられることになる。
一方の嵩さんは、母・登喜子さん、そして母方の祖母とともに新たな生活を始める。しかし登喜子さんは生活の糧を得るために裁縫や和裁、書道など多くの技術を身につけようと奮闘しており、家を留守にすることが多かった。結果的に、嵩さんは祖母の手によって主に育てられることになる。
やがて小学二年生となった嵩さんに、再び別れの時が訪れる。登喜子さんが再婚することになり、嵩さんを一時的に寛氏の家に預ける決断を下す。「お兄ちゃんなんだから、千尋に優しくしてあげてね。病気も治してもらいなさい」と言い残して、綺麗な着物に身を包み、白い日傘を差した母の後ろ姿を、千尋さんと並んで見送ったという場面は、やなせ氏の記憶に強く刻まれている。
当時の千尋さんは、寛氏夫妻に深く愛され、わがままながらも愛嬌のある性格で、地域の人々からも可愛がられていた。やなせ氏は後に「赤い着物」という詩の中で、当時の弟の姿を描写している。
その詩によると、千尋さんは女の子用の赤い着物を着て、髪もおかっぱに整えられていたという。これは「体が弱い子どもは女の子として育てると健康になる」という当時の迷信に基づくものであり、また養父母が女の子を望んでいた背景も影響していた。色白で丸顔、長いまつ毛という容姿から、知らない人は皆「かわいらしい娘さんですね」と声をかけたとされている。
すでに新しい家庭で愛情いっぱいに育てられている弟と、母に置いて行かれるという形でその家庭に迎え入れられた兄。2人の間には、言葉にしがたい距離感と、同時に切っても切れない深い絆が存在していた。朝ドラ『あんぱん』は、そうした兄弟の感情の揺れや再び家族になっていく過程を丁寧に描こうとしている。今後、物語がどのように展開し、2人の関係がどう変化していくのか、大きな見どころとなりそうだ。